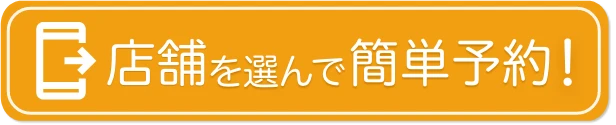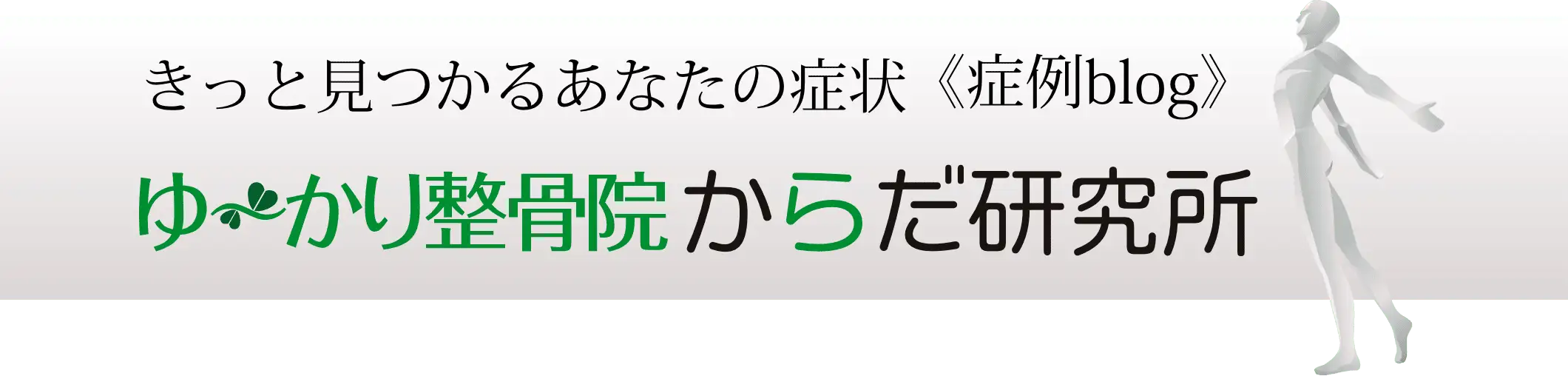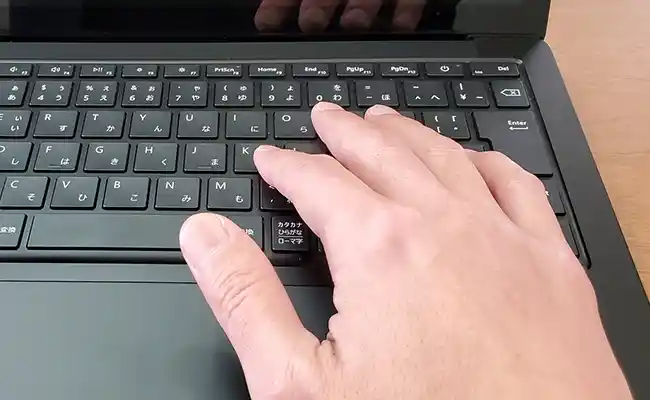肉離れ

- 「子供の運動会で張り切って走ったらブチッとなった」
- 「足をつくたびに電気が走るような激痛がある」
- 「テニスでダッシュしたら、激痛が走って歩けなくなった」
- 「こむらがえりだと思っていたが、痛みが引かない」
ゆ〜かり整骨院グループの肉離れの症状改善のながれ
肉離れについて
「こむらがえりだと思って安静にしていれば治ると思っていたが、痛みが引かない」という方が実は肉離れを発症していたケースも多くあります。
肉離れは筋肉(筋繊維)が断裂してしまった状態のことをいい、足のふくらはぎや太ももの損傷が多く見られます。「ブチッ!」「バチッ!」という筋肉の断裂音をご自身で感じるくらいの損傷では歩くのも困難となります。
適切な治療を行わないと再発を繰り返す
肉離れは筋肉が部分断裂または完全断裂した状態ですので、患部を伸ばしたり、押したり、力を入れたりすると痛みが走ります。重症になると、じっとしていても痛みを感じる場合もあり、筋肉が切れた患部が凹むこともあります。
肉離れは筋繊維に無理な力がかかったせいで断裂した状態で、切り傷と同じなのです。切り傷ができた場合は、切れた箇所の皮膚を寄せ合い、固定することで早期回復していきます。肉離れも同様に、損傷した筋繊維を適切に処置し、固定することが重要です。
適切な治療を行わないと、損傷した筋肉の硬結(炎症や鬱血が長期に及んで結合組織が増殖し、硬化すること)が残り、再発を繰り返す原因になってしまいます。
肉離れは年齢を問わず、スポーツ愛好家に発生することが多く見られます。大人の場合は加齢や運動不足により筋肉の柔軟性、筋力が低下、学生では筋疲労による柔軟性の低下などの原因で、肉離れを受傷するリスクが高まります。
肉離れの原因は?
〜ある日突然、筋肉がブチッと切れる!肉離れの本当の原因〜
「準備運動をせずに急に走ったら、太ももの裏がブチッとなった」 「テニスでダッシュした瞬間、ふくらはぎに激痛が走った」
肉離れは、スポーツや日常生活の中で急激な動作をした時に起こる筋肉の損傷です。実際には突発的に起きたように見えても、背後には筋肉の柔軟性低下や疲労の蓄積、準備運動不足などが積み重なっているのです。
肉離れが起こる原因
スポーツでは、バスケットボールやバレーボールなどのジャンプ競技、サッカーなどのコンタクトスポーツで、着地の失敗や接触プレーによって捻挫することが多く見られます。運動部の学生さんや社会人チームで活動している方に多く発生します。
また、日常生活では階段の昇り降り、段差につまずく、道路でコケるなど、誰にでも起こりうる状況で捻挫が発生します。
急激な動作が肉離れの引き金に」
肉離れは、踏み込み・ダッシュ・ジャンプなどの動作でふくらはぎの筋肉(下腿三頭筋)が急激に収縮した時や、着地動作などで急に筋肉が伸ばされたりした時に発生するケースが多いです。
ふくらはぎの肉離れは、ダッシュや急ブレーキ、ジャンプするときや着地の動作で、ふくらはぎの伸び縮みが強く起こるため筋肉にストレスがかかりやすい動作となり、筋肉が耐え切れず損傷・断裂することで起こります。
太ももの裏(大腿二頭筋・ハムストリングス)は、
「準備運動をせずに急に走った」
「普段やらない運動をした」
「足を滑らせて踏ん張った」
など、足に比較的大きな力を入れた時、片足に全体重が乗り、大きい筋肉で地面を蹴る動作をしているときに発生する傾向が強いです。
肉離れは筋肉が急激に引き伸ばされることで筋繊維が切れてしまい起こるので、熱感、炎症性の痛み、腫脹、皮下出血が起こります。軽度の場合、自力での歩行は可能ですが痛みを伴います。重度になると痛みが強く自力での歩行が困難な場合もあります。
筋肉の疲労蓄積が大きな原因
その他の原因としては、転倒しそうになって踏ん張ったり、足を滑らせた時などちょっとした動作なのに、肉離れを発症する場合は、筋肉の疲労が関係していることも考えられます。オーバーユースにより疲労が蓄積され、硬化してしまった筋肉に負荷をかけ続けることで筋繊維が切れて肉離れを起こします。
季節の変わり目は特に注意
また、季節の変わり目など気温差が激しい時期などは、血液循環が悪くなりやすく筋肉の柔軟性が低下しやすく、筋肉が切れやすいので、季節の変わり目に多く見られることも特徴です。
水分不足や身体の冷えも原因に
身体の水分量が低下すると血流が悪くなり栄養が行き届かなくなります。その結果、筋肉は硬化しやすくなり切れやすくなります。また、身体の冷えも筋肉の柔軟性を低下させ、肉離れのリスクを高めます
適切な処置が重要
天王町接骨院、ゆ〜かり整骨院では、問診でいつ、どのように痛めたのか(発生機序)、どこが痛いのか(触診)、損傷の程度などを確認(視診)しながら施術の方法、処置の仕方を決めていきます。受傷からどのくらい時間が経過しているかによって処置の仕方が変わってきますので、最善の方法をご提案します
肉離れの施術の流れ
〜肉離れのつらい痛みの改善から、安心して日常動作やスポーツができる身体づくりまで〜
肉離れは「急激な動作をした瞬間に筋肉がブチッと切れる音とともに激痛が走る」という発症パターンが多く、重症の場合は歩行も困難になります。軽度の場合でも、痛みや違和感が長期間残ることがあります。
天王町接骨院、ゆ〜かり整骨院では、肉離れの回復を「初期・中期・後期・メンテナンス期」の4段階に分け、それぞれの状態に合わせた施術を行います。早期に炎症を抑え、損傷した筋肉を適切に修復させ、再発しにくい身体づくりまでサポートします。
※治療初期からメンテナンス期までの流れは、多い事例でご紹介しています。全ての方が当てはまるわけではございません。また、患部の状態によっては専門医(医師)をご紹介することもございますので、ご了承ください。
《初期》肉離れの施術
〜肉離れの痛みを残さないために最も大事な初期治療〜
肉離れを起こした筋組織(患部)に痛みや熱感、腫れなどがある炎症期は、痛みを抑えることを目的とした施術を行います。
この初期治療の期間はおおよそ2週間が目安です。特に受傷直後の対応が最も重要なため、週2〜3回程度の通院ペースをおすすめしています。早期に炎症を抑え、損傷した筋繊維を適切に修復させることで、次の回復ステップへとスムーズに移行できます。
「筋肉が切れた部分がズキズキ痛む」「足をつくたびに電気が走るような激痛がある」など、急性期はとてもつらい状態です。この段階では無理に動かすよりも、痛みの緩和と炎症の沈静化が最優先となります。
◎物理療法機器で炎症を軽減
天王町接骨院、ゆ〜かり整骨院では、治療初期にまず熱感、腫脹、皮下出血を軽減させるためにアイシング、ハイボルテージ、マイクロカレントなどの物療機器で患部の炎症を引かせます。
ハイボト治療は神経に作用し、痛みの鎮静や神経の興奮を鎮める効果が期待できます。マイクロカレントは微弱電流を流すことで、損傷した組織の修復を促進します。
◎筋肉調整と圧迫固定に
次に、損傷部位の周囲の固まった筋肉を緩め(筋肉調整)、血流を促してから、損傷部位を圧迫固定(包帯固定)します。
肉離れは筋繊維が断裂した状態で、切り傷と同じです。切れた筋繊維を寄せ合い、固定することで早期回復を図ります。
施術を続けていくと、患者様から「痛みが落ち着いてきた」「熱感が引いてきた」「歩けるようになった」「腫れが引いてきた」といったお声をいただくのがこの肉離れの初期段階です。
《中期》肉離れの施術
〜筋肉の痛みを抑えつつ、柔軟性を回復させる大切な時期〜
中期は、損傷した筋肉の機能を改善させることを目的として施術を行います。
この中期の施術期間は、初診からおおよそ3〜5週間が目安です。特にこの時期は「痛みが和らいだからもう大丈夫」と通院をやめてしまう方もいますが、筋肉の柔軟性を取り戻し、再断裂を防ぐためには週1〜2回の通院を継続することが重要です。
ここでしっかり治療を行うかどうかで、その後の回復スピードや再発リスクが大きく変わってきます
急性期の激しい痛みが落ち着いたあとも「患部を伸ばすと痛い」「力を入れると痛みが出る」といった制限が強く残ります。
◎筋肉調整で硬結を緩める
肉離れは受傷から2〜3週間が最も再断裂のリスクが高いので、筋肉調整(柔整マッサージ、トリガーポイント療法)を施し筋肉を緩めて血流を改善させ、損傷部位の再生、修復を早めます。
炎症や鬱血により軟部組織や筋肉が硬結(柔らかい組織が硬くなること)すると肉離れの再発が起こりやすくなるため、この硬結をしっかり緩め血液循環を良くしていくことが大切です。硬結が強い場合にはハイボト治療をします。
◎テーピングで段階的に負荷を上げる
筋肉からの出血が止まれば、包帯固定からテーピングに変更し、少しずつ損傷した筋肉への負荷を上げていきます。患部の動きを取り戻す段階のため、再断裂のリスクもあるので焦らずに日常生活をしていただくことで、正常な筋肉の柔軟性、動きを取り戻していきます。
施術を続けていくと、患者様から「伸ばしても痛くなくなった」「力を入れられるようになった」「普通に歩けるようになった」「階段が楽になった」といったお声をいただくのがこの肉離れの中期段階です。
《後期》肉離れの施術
〜筋肉の動きを整え、良い状態を安定させる大切な時期〜
後期は、肉離れがある程度回復した状態で、患者様の日常生活動作に制限をかけず、やりたいことを行動してもらいながら経過を観察する期間です。
この後期の施術は、通常週1回程度の通院を目安に2〜3週間ほど継続するのがおすすめです。正しい身体の動かし方を身につけ、筋肉に負担をかけない生活習慣を定着させることで、改善した良い状態を安定させることができます。
肉離れは、発症から完治までに6〜8週間かかるのが一般的です。初期・中期の施術で痛みは軽減し、筋肉の柔軟性も改善してきますが、この後期の段階では「患部に違和感が残る」「運動すると痛みが出る」といった症状が出やすくなります。
◎段階的に負荷をかける運動指導
この時期に特に大切なのが、段階的に負荷をかけながら筋肉の機能を回復させることです。日常生活では、ふくらはぎに負荷が加わるように階段を利用したり、カーフレイズ(ふくらはぎの筋力強化)でふくらはぎ局所に負荷をかける運動を始めます。
軽いジョギングを開始するのは、痛めた方の「足をかばう動作」がなくなってから行うよう指導しています。足をかばう動作は、関節の動きの効率を落とすだけでなく、腰や膝など余計な箇所に痛みをもたらします。
◎硬結を緩めて再発を防ぐ
損傷した筋肉の硬結が残っていると肉離れを再発する可能性が高くなります。
後期の施術において患者様お一人おひとりの生活スタイルに合わせた指導を行います。
施術で筋肉の動きをさらにスムーズに整えるとともに、運動の仕方・ストレッチ方法といった日常動作を見直し、再び「肉離れを起こす」とならないようにサポートします。
上記の施術でも筋肉が緩まない場合も多く、その原因が骨格の歪みである場合は骨格調整と筋肉調整で筋肉にかかる負荷を取り除き、再発しにくい身体をつくっていきます。
施術を続けていくと、患者様から「違和感がなくなった」「運動に復帰できた」「走れるようになった」「以前のようにプレーできる」といったお声をいただくのがこの肉離れの後期段階です。
《メンテナンス期》肉離れの施術
〜肉離れを再発させないための身体づくり〜
◎なぜ肉離れは再発しやすいのか
肉離れが回復し、動いていると痛めた部位や周囲の筋肉が硬くなります。これは瘢痕(はんこん)組織といい、競技に復帰しても、再び同じ箇所を痛めてしまうのはこのためです。
瘢痕(はんこん)組織は、筋組織が再生した後、つまり治癒した後に出来上がるため、瘢痕(はんこん)組織が出ないようにすることはできません。動きながら、瘢痕(はんこん)組織を緩め、痛める前と同じように伸び縮みできて初めて《治った》となるのです。
そのため、痛みが落ち着いたあとも「再発を防ぐためのメンテナンス」がとても大切です。
◎骨格調整と筋肉調整で柔軟性を高める
肉離れを起こしやすい原因は、大人の場合は加齢や運動不足、学生の場合は筋疲労による柔軟性の低下です。
天王町接骨院、ゆ〜かり整骨院では、まず骨格調整で骨格の歪みを改善し、筋肉にかかる負荷を軽減します。次に、筋肉調整(柔整マッサージ、トリガーポイント療法)で筋肉を緩めて血流を良くし、老廃物を流れやすくします。
これにより、筋肉の柔軟性を高め、身体の姿勢バランスを整えることで、肉離れを起こしにくい身体づくりをサポートします。
◎EMSで体幹を安定させる
整えた姿勢(骨格バランス)を維持するために、EMS(電気刺激でインナーマッスルを刺激する治療機器)でインナーマッスルを鍛えることで、体幹を安定させ下肢にかかる負担を減らします。
継続的なスポーツをしている方で、肉離れを繰り返す方にぜひお勧めしたいのがこのメンテナンスです。筋肉に疲労を蓄積させないことが肉離れの防止になります。スポーツ選手はもちろん、普段長い距離を歩く方や電車で何時間も立ちっぱなしの方は、ふくらはぎに疲労が溜まっている可能性があります。疲労が溜まっている状態で、急に走ったりジャンプをしたりするととても危険です。
通院ペースは症状や生活習慣によって異なりますが、一般的には月1〜2回の定期的なメンテナンスを続けることで、良い状態を安定させやすくなります。単に痛みを取るだけでなく、再発しにくい身体を作ることこそが、このメンテナンス期の大きな目的です。
肉離れの予防について
〜肉離れを起こさない身体をつくるために〜
肉離れは、発症すると強い痛みによって日常生活やスポーツに大きな影響を及ぼします。また、一度発症すると再発しやすいという特徴があります。そのため、予防と再発防止がとても重要です。
水分不足に注意
身体の水分量が低下すると血流が悪くなり栄養が行き届かなくなります。
その結果、筋肉は硬化しやすくなり切れやすくなります。こまめな水分補給が大事です。 特に運動中や暑い時期は、意識的に水分を摂取しましょう。スポーツドリンクなどで電解質も補給すると効果的です。
身体の冷えは厳禁
自分の知らないところで筋肉は冷えています。窓を開けて寝る、冷たい飲み物が好き、冷房をつけていることが多い、お風呂をシャワーで済ませることが多いなどで、知らぬ間に身体を冷やすのも肉離れの原因となります。
湯船に浸かり温まることや夏でも長いズボンを履いて寝るなど、日常生活のひと工夫が予防になります
運動前のウォーミングアップとストレッチ
多くの方が、「これくらいなら…」「この程度なら…」と準備運動を省略して肉離れを起こします。ウォーミングアップ、ストレッチや準備運動をしてから運動をする習慣を身につけましょう。
◎アキレス腱伸ばし
壁に手をつき、片足を後ろに引いてかかとを床につけたまま前に体重をかけます。ふくらはぎがしっかり伸びているのを感じながら20〜30秒キープ。左右それぞれ行いましょう。運動前後、競技中にも行って柔軟性の低下を防ぎ、肉離れを予防しましょう。
◎太もも裏のストレッチ
座った状態で片足を伸ばし、つま先に向かって上体を倒します。太もも裏(ハムストリングス)が伸びているのを感じながら20〜30秒キープ。
日常生活で意識したい予防法
十分な睡眠をとる 睡眠不足は筋肉の回復を妨げ、筋疲労を蓄積させます。しっかり眠ることで筋肉のコンディションを保ちましょう。
◎定期的な運動習慣
普段から適度な運動を続けることで、筋肉の柔軟性と筋力を維持できます。急に激しい運動をするのではなく、日常的に身体を動かす習慣をつけましょう。
◎バランスの良い食事
タンパク質が不足すると筋肉の修復力が落ち、肉離れのリスクが高まります。肉、魚、卵、大豆製品などをバランスよく摂取しましょう。
◎疲労を溜めない
スポーツ選手はもちろん、長時間立ちっぱなしの仕事や長距離を歩く方は、ふくらはぎに疲労が溜まりやすいです。定期的にストレッチやマッサージでケアしましょう。
天王町接骨院、ゆ〜かり整骨院では、施術とあわせて筋肉の柔軟性を高める簡単なストレッチや運動方法を指導しています。ご自宅で継続することで、再発予防にもつながります。
肉離れについてよくある質問(FAQ)
Q.肉離れとこむらがえりの違いは何ですか?
A. こむらがえりは筋肉が一時的に痙攣して起こる痛みで、通常は数分で治まります。一方、肉離れは筋繊維が断裂した状態で、痛みが長く続き、患部を伸ばしたり押したりすると痛みが出ます。「こむらがえりだと思っていたが痛みが引かない」という場合は肉離れの可能性があります。
Q.肉離れは放っておいても自然に治りますか?
A. 軽度の肉離れであれば自然に痛みは軽減しますが、適切な処置をしないと筋肉の硬結が残り、再発しやすくなります。早期に施術を受けることで、適切に筋繊維が修復され、再発を防ぐことができます。
Q.なぜ肉離れを繰り返してしまうのですか?
A. 以前の肉離れで筋肉に硬結(瘢痕組織)が残っているためです。この硬結があると筋肉の柔軟性が低下し、再び同じ箇所を痛めやすくなります。メンテナンス治療で硬結を緩め、筋肉の柔軟性を取り戻すことが重要です。
Q.改善までにはどれくらいかかりますか?
A. 個人差はありますが、軽度の肉離れで4〜6週間、重度の肉離れで6〜8週間ほどかかるのが一般的です。ただし、受傷後すぐに適切な処置を行うことが重要で、放置すると回復に時間がかかります。
Q.通院の頻度はどのくらいですか?
A. 急性期は週2〜3回の集中的な施術で炎症を抑え、損傷した筋繊維を適切に修復させます。中期は週1〜2回で筋肉の柔軟性を取り戻し、後期以降は週1回程度で良い状態を安定させます。症状が落ち着いたら、月1〜2回のメンテナンスがおすすめです。
Q.湿布だけでは治らないのですか?
A. 湿布は痛みを和らげる効果はありますが、断裂した筋繊維を適切に修復させるには専門的な治療が必要です。損傷した筋繊維を寄せ合い、固定することで早期回復を図ります。湿布だけでは筋肉の硬結が残り、再発しやすくなります。
Q.自宅でできる予防法はありますか?
A. はい。運動前後のストレッチ・こまめな水分補給・身体を冷やさない・十分な睡眠・バランスの良い食事が有効です。当院では再発を防ぐための筋肉の柔軟性を高めるストレッチも指導しています。
Q.スポーツにいつ復帰できますか?
A. 痛みが落ち着き、筋肉の柔軟性が十分に回復し、患部に違和感がなくなってからの復帰が望ましいです。特に「足をかばう動作」がなくなってから運動を再開することが重要です。無理に早期復帰すると再断裂や慢性化のリスクが高まります。担当の柔道整復師と相談しながら、段階的に復帰しましょう。
Q.季節の変わり目に肉離れが多いのはなぜですか?
A. 季節の変わり目は気温差が激しく、血液循環が悪くなりやすく筋肉の柔軟性が低下しやすいためです。特に寒暖差が大きい時期は、入念なウォーミングアップと水分補給、身体を冷やさないよう注意しましょう。
Q.アイシングはいつまで続けるべきですか?
A. 受傷直後から熱感や腫れが落ち着くまで(通常2〜3日間)はアイシングが効果的です。20分冷やして5分休憩を繰り返します。熱感が落ち着いたら、血流を促進させるための温熱療法に切り替えます。
監修:ゆ〜かり整骨院グループ 株式会社アザース 柔道整復師チーム
※柔道整復師とは、骨折、脱臼、打撲、捻挫などの外傷に対し、手術や薬に頼らず、手技療法や物理療法、運動指導を駆使して、患者の自然治癒力を最大限に引き出す治療を行う国家資格を持つ医療技術職です。
肉離れについては下記に各院にご相談ください。
《症状改善の流れ》あなたのお悩みはどれですか?
肩こりを治すとゴルフのスライスが直る!
2026年2月2日
筋骨格系の専門家が語る「肩こり」と「ゴルフ上達」の深い関係 かつてゴルフといえば中高年のレジャーというイメージが強いものでした。 しかし現在では状況が大きく変わっています。松山英樹選手のマスターズ制覇や渋野日向子選手の全 […]
ゴルフスライス巻き肩肩こりふくらはぎが痛くて歩けない……「肉離れ」
2025年9月20日
ふくらはぎの「肉離れ」その原因とは? ふくらはぎの肉離れは、スポーツの場面でよく起こる代表的な外傷です。 たとえば、膝を曲げた状態でジャンプするときや、地面を強く蹴った瞬間などです。テニスでボールを追いかけるときの後ろ足 […]
サッカースポーツ外傷ふくらはぎの痛み肉離れ朝起きたら、首が大変なことに!「寝違え」
2025年9月20日
寝違えて首が痛くなってしまったら…… 寝違えの多くは、寝ているときの姿勢が原因です。長時間にわたり首に負担がかかる体勢が続くことで、痛みが出やすくなります。 痛みがあるときは炎症が起きています。自己流でストレッチやマッサ […]
ストレッチ寝違え首の痛み