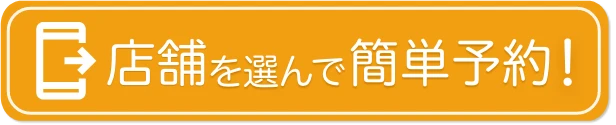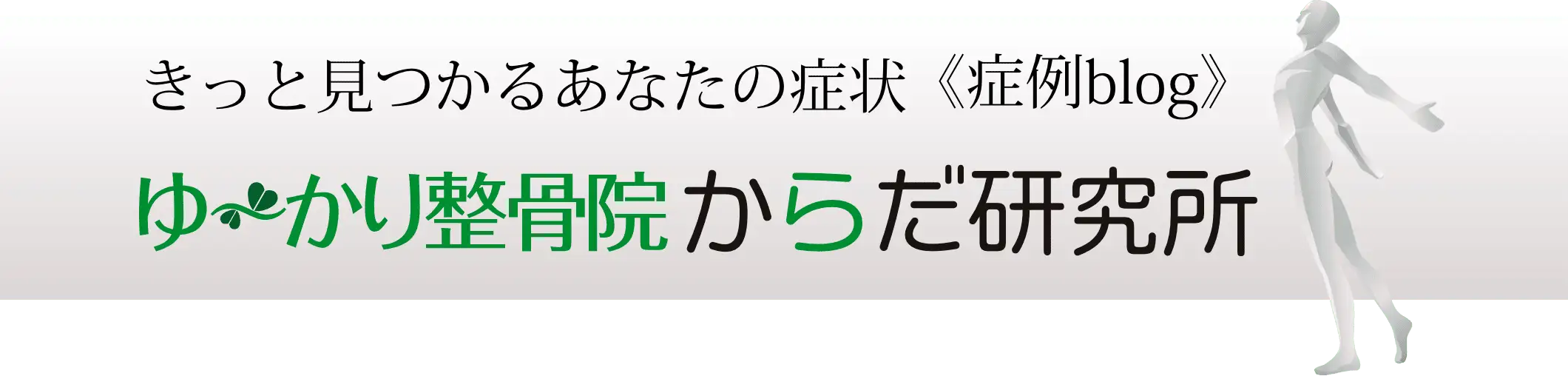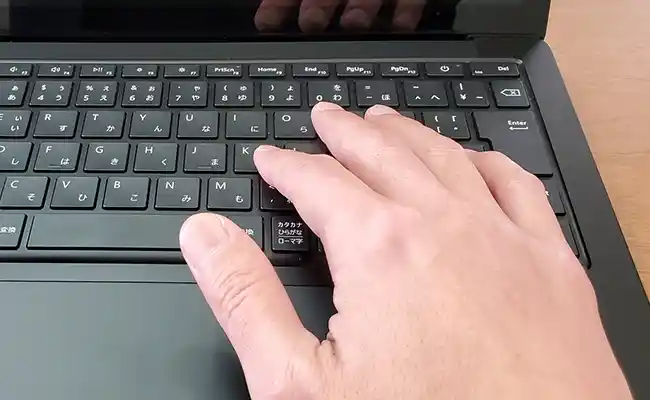足関節捻挫(そくかんせつねんざ)

- 「駅の階段を降りている最中に段差に躓いて足首を捻ってしまった」
- 「バスケのプレー中にバランスを崩して足首を挫いた」
- 「何度も同じ側の足首を捻挫してしまう」
- 「足首の捻挫が治ったと思っていたのに、また痛くなってきた」
ゆ〜かり整骨院グループの足関節捻挫(そくかんせつねんざ)の症状改善のながれ
足関節捻挫(そくかんせつねんざ)について
「ちょっと捻っただけだから」「湿布を貼っておけば治るだろう」と軽く考えていませんか?
足関節捻挫を放置すると、靭帯が伸びたまま修復され、繰り返し捻挫を起こす原因になってしまいます。
軽傷の場合であってもしっかりと治療をして良いカタチで関節を固定しておかないと、靭帯が緩いままになってしまい、再び捻挫を繰り返す原因になってしまうということです。
靭帯は一度伸びてしまうと元の長さには戻りません。軽度な「伸び」の場合は、適切な処置をすることで日常生活に支障がないレベルまで回復する可能性があります。
しかし、靭帯が伸びたまま(緩んだまま=関節が不安定なまま)では、足首を捻ってしまうリスクが高く、足関節捻挫を繰り返す原因となるだけでなく、捻挫を繰り返すことで、足首の骨・関節が変形するリスクが高まります。
放置すると回復までに長期間を要したり、慢性的な痛みにつながることもあります。
そもそも捻挫とは、骨と骨をつなぐ靭帯の損傷です。足関節捻挫は、足首を内側に捻って生じる内反捻挫がおよそ9割を占め、その多くは外側くるぶし周囲にある靱帯の損傷です。
足首の捻挫は一生のうちに80%以上の人が経験する怪我の一つであり、スポーツだけではなく、歩行時のつまずき・転倒など日常生活の中でも多く発生します。
軽傷の場合で2週間程度、重傷であれば6〜8週間を損傷してしまった靭帯の修復に時間を要します。
早めに受診された場合、適切な処置をすることで、靭帯が正しく修復され、再発を防ぐことができます。
足関節捻挫(そくかんせつねんざ)の原因は?
〜ある日突然、足首を捻った!繰り返す捻挫の本当の原因〜
「階段を降りている時に足首を捻ってしまった」
「スポーツ中にジャンプの着地で足首を挫いた」
足関節捻挫は、スポーツや日常生活の中で誰にでも起こりうる頻度の高い外傷です。
足関節捻挫が起こる原因
スポーツでは、バスケットボールやバレーボールなどのジャンプ競技、サッカーなどのコンタクトスポーツで、着地の失敗や接触プレーによって捻挫することが多く見られます。運動部の学生さんや社会人チームで活動している方に多く発生します。
また、日常生活では階段の昇り降り、段差につまずく、道路でコケるなど、誰にでも起こりうる状況で捻挫が発生します。
捻挫を繰り返す原因は「靭帯が伸びたまま」
一度捻挫を経験すると「何度も同じ側の足首を捻挫してしまう」という方が多く見られます。来院された患者さんで、「同じ側の足首を、何度も捻挫している」と聞くことがあります。そんな、捻挫を繰り返す患者さんを診せていただくと、ある”共通点”があります。
その共通点とは、足首の関節が捻挫をした時の位置で固定されてしまっている状態であり「足関節の構造と機能が正常ではない」ということです。
そういった患者さんは、治療を受けずに「痛みは無くなった」ので、「その捻挫は治った」と思われているのだろうと思いますが、私たちの視点では、骨・関節が正常な位置に戻っており、関節運動や歩行が痛みなく行うことができなければ「治った」とは判断しません。
足首を捻った時は、靭帯が切れて骨・関節の位置が変わってしまうので、時間が経過し炎症が治っても足首が元の位置に戻らないままでは、足関節の構造と機能は正常に戻りません。
靭帯が伸びたまま(緩んだまま=関節が不安定なまま)動くことで、関節に負荷をかけて慢性的な炎症を繰り返し、足首を内側に捻っていないのに痛みが引かない状態となっているケースが多く見られます。
適切な治療の重要性
腫れがそれほど目立たず痛みも我慢できる程度であれば、様子をみながら自分でセルフケアでOKですが、靭帯部分を押して痛む場合、腫れがある場合、関節の不安定さを感じる場合などは治療が必要なので、早めの受診をおすすめします。
「自然に治るだろう」「たかが捻挫」と放置すると、かえって長引きやすく、捻挫を繰り返す原因になってしまうのです
足関節捻挫(そくかんせつねんざ)の施術の流れ
〜足関節捻挫のつらい痛みの改善から、安心して日常動作やスポーツができる身体づくりまで〜
足関節捻挫は「足首を捻った瞬間に激しい痛みが走る」という発症パターンが多く、捻挫直後から腫れや内出血が見られることもあります。
急激な痛みは数日から1週間ほどで落ち着く場合もありますが、その後も足首に不安定感が残ったり、歩行時に痛みが出たりすることが少なくありません。
天王町接骨院、ゆ〜かり整骨院では、足関節捻挫の回復を「初期・中期・後期・メンテナンス期」の4段階に分け、それぞれの状態に合わせた施術を行います。まず骨・関節を正常な位置に戻し、靭帯が適切に修復されるよう固定します。また、メンテナンス期には足首の安定性を高めて、足関節捻挫の再発予防をします。
※治療初期からメンテナンス期までの流れは、多い事例でご紹介しています。全ての方が当てはまるわけではございません。また、患部の状態によっては専門医(医師)をご紹介することもございますので、ご了承ください。
《初期》足関節捻挫(そくかんせつねんざ)の施術
〜捻挫の痛みを残さないために最も大事な初期治療〜
足関節捻挫の施術は、まず「痛みを抑えること」と「骨・関節を正常な位置に戻すこと」から始まります。
この初期治療の期間はおおよそ1〜2週間が目安です。特に捻挫直後の対応が最も重要なため、週2〜3回程度の通院ペースをおすすめしています。治療の間隔が開かないように治療を行うことで、その後の回復がスムーズになります。
「足首がズキズキ痛む」「体重をかけると激痛が走る」など、急性期はとてもつらい状態です。この段階では無理に動かすよりも、痛みの緩和と炎症の沈静化が最優先となります。
◎ハイボルテージ療法で神経調整
天王町接骨院、ゆ〜かり整骨院では、治療初期にまずハイボト治療(高電位圧治療・電気鍼)で施し、筋肉や運動神経を刺激し筋収縮を起こすことで感覚神経を刺激して痛みの軽減や種々の反射的な治療効果、早期回復が期待できます。
◎整復で骨・関節を正常な位置に
「神経調整」を施した後は、足関節の整復で「骨格調整」を施します。骨折した状態をもとの位置に戻すことを「整復」と言います。
◎包帯固定で靭帯の修復を促す
整復した箇所を、包帯で動かないようにする事を「固定」と言います。
骨・関節を正常な位置に戻してから包帯固定を施すことで、靱帯が伸びたまま修復されることを防ぎ、早く正しく修復するよう治療を行います。この初期治療が、その後の「治り方」を大きく左右します。
施術を続けていくと、患者様から「痛みが落ち着いてきた」「腫れが引いてきた」「体重をかけられるようになった」「歩けるようになってきた」といったお声をいただくのがこの足関節捻挫の初期段階です
《中期》足関節捻挫(そくかんせつねんざ)の施術
〜足首の痛みを抑えつつ、可動域を回復させる大切な時期〜
中期では、靭帯の炎症や足首の腫れが引き、痛みのレベルが下がったら、固まった関節の動きを出す治療に移ります。
この中期の施術期間は、初診からおおよそ3〜6週間が目安です。
特にこの時期は「痛みが和らいだからもう大丈夫」と通院をやめてしまう方もいますが、可動域を取り戻し、靭帯をしっかり修復させるためには週1〜2回の通院を継続することが重要です。ここでしっかり治療を行うかどうかで、その後の回復スピードや再発リスクが大きく変わってきます。
急性期の激しい痛みが落ち着いたあとも「足首が動かしづらい」「歩くと痛みが出る」「足首に不安定感がある」といった運動制限が残ります。
◎筋肉調整と運動療法で可動域を広げる
初期治療が終わってからの2〜4週間は、患部を中心とした筋肉と関節の動きが良くなるように、運動療法の施術や柔整マッサージなど筋肉調整によって組織の血液循環を推進します。運動療法とハイボト治療も併用しながら、細胞の修復を促します。
◎日常生活動作の指導
また、できるだけ早く痛みを取り、日常生活を送れるよう関節の動かし方・歩き方の指導などを行い、日常生活動作の注意点や指導をしていきます。これにより、足首の動きを妨げている根本的な要因を改善していきます。
施術を続けていくと、患者様から「足首が動かしやすくなった」「歩く時の痛みが減った」「階段の上り下りが楽になった」「運動できるようになってきた」といったお声をいただくのがこの足関節捻挫の中期段階です。
《後期》足関節捻挫(そくかんせつねんざ)の施術
〜足首の動きを整え、良い状態を安定させる大切な時期〜
後期は、経過観察の期間になります。患者様の日常生活動作や趣味の運動などを行っても痛みや症状が出ないか、積極的な治療をせずに定期的に患部の状態を検査(観察)することをいいます。
この後期の施術は、通常週1回程度の通院を目安に2〜4週間ほど継続するのがおすすめです。正しい歩行や関節の動かし方を身につけ、足首に負担をかけない生活習慣を定着させることで、改善した良い状態を安定させることができます。
足関節捻挫は、発症から完治までに軽度で2週間程度、重度で6〜8週間かかるのが一般的です。初期・中期の施術で痛みは軽減し、足首の可動域も改善してきますが、この後期の段階では「特定の動作で足首に違和感が残る」「スポーツや日常生活の動作で不安を感じる」といった症状が出やすくなります。
◎セルフケアと歩行指導
この時期に特に大切なのが、正しい歩き方を意識することと足首のストレッチなどのセルフケアです。
姿勢や歩行バランスが崩れていないか、日常的なケアが継続できているかを確認しながら、残存する足首の可動域制限をさらに改善していきます。
天王町接骨院、ゆ〜かり整骨院では、後期の施術において患者様お一人おひとりの生活スタイルに合わせた指導を行います。施術で足関節の動きをさらにスムーズに整えるとともに、歩き方・関節の動かし方といった日常動作のクセを見直し、再び「足首が痛い」「捻挫を繰り返す」とならないようにサポートします。
施術を続けていくと、患者様から「違和感がなくなった」「スポーツに復帰できた」「不安なく動けるようになった」「以前のように走れるようになった」といったお声をいただくのがこの足関節捻挫の後期段階です。
《メンテナンス期》足関節捻挫(そくかんせつねんざ)の施術
〜足関節捻挫を再発させないための身体づくり〜
◎なぜ足関節捻挫は再発しやすいのか
足首を支える筋肉(腓骨筋、後脛骨筋など)が弱いと、歩行時や運動時のバランスが不安定になり、足首を捻りやすくなります。
また、以前の捻挫で靭帯が伸びたまま修復されている場合、関節が不安定な状態のため、再び捻挫を起こしやすい状態になっています。そのため、痛みが落ち着いたあとも「再発を防ぐためのメンテナンス」がとても大切です
◎運動療法とストレッチ指導で安定性を高める
ゆ〜かり整骨院では、運動療法とストレッチ指導を通じて、足首の柔軟性と安定性を保ち、正しい歩行パターンを維持できる身体づくりをサポートします。また、バランストレーニングや足関節周囲の筋力強化トレーニングも指導し、再発しにくい身体を作ります。
◎EMSで足関節周囲の筋力強化
さらに、必要に応じてEMSを用いて、普段の生活だけでは鍛えにくい足関節周囲の筋肉を効率的に活性化。これにより、骨格を支える筋肉の機能を向上させ、正しい姿勢とバランスを維持できる身体づくりをサポートします。
通院ペースは症状や生活習慣によって異なりますが、一般的には月1〜2回の定期的なメンテナンスを続けることで、良い状態を安定させやすくなります。単に痛みを取るだけでなく、再発しにくい身体を作ることこそが、このメンテナンス期の大きな目的です。
足関節捻挫(そくかんせつねんざ)の予防について
〜足関節捻挫にならない身体をつくるために〜
足関節捻挫は、発症すると痛みによって日常生活や運動に大きな影響を及ぼします。また、一度捻挫すると繰り返しやすいという特徴があります。そのため、予防と再発防止がとても重要です。
捻挫を予防するための運動 ストレッチ運動(特にふくらはぎの筋肉や股関節の筋肉)で予防しましょう。足関節捻挫の予防および再発予防のための運動をご紹介します。
足首のストレッチ
片足立ちを1分間キープする練習を、左右それぞれ行いましょう。慣れてきたら目を閉じて行うと、より効果的です。
天王町接骨院、ゆ〜かり整骨院では、施術とあわせて足首の安定性を高める簡単なトレーニングやストレッチを指導しています。ご自宅で継続することで、再発予防にもつながります。
日常生活で意識したい予防法 足関節捻挫を防ぐには、生活習慣そのものを整えることが大切です。
運動前後のケア
運動の前には筋肉を緩めるために、ウォーミングアップしましょう。
運動の後には筋肉に疲労物質(乳酸)を残さないために、クールダウンしましょう。
適切な靴の選択
自分の足にフィットした、歩きやすい靴をはきましょう。ヒールの高い靴や、足首のサポートが不十分な靴は捻挫のリスクを高めます。
足首周囲の筋力強化
つま先立ちやかかと歩きなど、日常的に足首周囲の筋肉を使う運動を取り入れましょう。
足関節捻挫(そくかんせつねんざ)についてよくある質問(FAQ)
Q.捻挫は放っておいても自然に治りますか?
A. 痛みは自然に軽減することもありますが、適切な治療をしないと靭帯が伸びたまま修復され、関節が不安定になり捻挫を繰り返す原因になります。早期に施術を受けることで、適切に靭帯が修復され、再発を防ぐことができます。
Q.なぜ同じ側の足首ばかり捻挫してしまうのですか?
A. 以前の捻挫で靭帯が伸びたまま修復され、関節が不安定な状態になっているためです。骨・関節が正常な位置に戻っていないと、足首を捻りやすくなります。適切な治療と固定、そしてメンテナンスで再発を防ぐことができます。
Q.改善までにはどれくらいかかりますか?
A. 個人差はありますが、軽度の捻挫で2週間程度、重度の捻挫で6〜8週間ほどかかるのが一般的です。ただし、受傷後すぐに適切な処置を行うことが重要で、放置すると回復に時間がかかります。
Q.通院の頻度はどのくらいですか?
A. 急性期は週2〜3回の集中的な施術で炎症を抑え、骨・関節を正常な位置に戻します。中期は週1〜2回で可動域を広げ、後期以降は週1回程度で良い状態を安定させます。症状が落ち着いたら、月1〜2回のメンテナンスがおすすめです。
Q.湿布だけでは治らないのですか?
A. 湿布は痛みを和らげる効果はありますが、骨・関節を正常な位置に戻し、靭帯を適切に修復させるには専門的な治療が必要です。湿布だけでは靭帯が伸びたまま修復され、捻挫を繰り返す原因になります。
Q.自宅でできる予防法はありますか?
A. はい。足首のストレッチ・バランストレーニング・運動前後のウォーミングアップとクールダウン・適切な靴の選択が有効です。当院では再発を防ぐための足首強化トレーニングも指導しています。
Q.スポーツにいつ復帰できますか?
A. 痛みが落ち着き、足首の可動域が十分に回復し、関節の安定性が確保されてからの復帰が望ましいです。無理に早期復帰すると再発や慢性化のリスクが高まります。担当の柔道整復師と相談しながら、段階的に復帰しましょう。
Q.テーピングは効果がありますか?
A. はい。テーピングは足首の安定性を高め、捻挫の予防や再発防止に効果的です。当院では適切なテーピング方法も指導しています。ただし、テーピングだけでなく、根本的な筋力強化とバランス改善が重要です。
監修:ゆ〜かり整骨院グループ 株式会社アザース 柔道整復師チーム
※柔道整復師とは、骨折、脱臼、打撲、捻挫などの外傷に対し、手術や薬に頼らず、手技療法や物理療法、運動指導を駆使して、患者の自然治癒力を最大限に引き出す治療を行う国家資格を持つ医療技術職です。
足関節捻挫(そくかんせつねんざ)については下記に各院にご相談ください。
《症状改善の流れ》あなたのお悩みはどれですか?
肩こりを治すとゴルフのスライスが直る!
2026年2月2日
筋骨格系の専門家が語る「肩こり」と「ゴルフ上達」の深い関係 かつてゴルフといえば中高年のレジャーというイメージが強いものでした。 しかし現在では状況が大きく変わっています。松山英樹選手のマスターズ制覇や渋野日向子選手の全 […]
ゴルフスライス巻き肩肩こりふくらはぎが痛くて歩けない……「肉離れ」
2025年9月20日
ふくらはぎの「肉離れ」その原因とは? ふくらはぎの肉離れは、スポーツの場面でよく起こる代表的な外傷です。 たとえば、膝を曲げた状態でジャンプするときや、地面を強く蹴った瞬間などです。テニスでボールを追いかけるときの後ろ足 […]
サッカースポーツ外傷ふくらはぎの痛み肉離れ朝起きたら、首が大変なことに!「寝違え」
2025年9月20日
寝違えて首が痛くなってしまったら…… 寝違えの多くは、寝ているときの姿勢が原因です。長時間にわたり首に負担がかかる体勢が続くことで、痛みが出やすくなります。 痛みがあるときは炎症が起きています。自己流でストレッチやマッサ […]
ストレッチ寝違え首の痛み