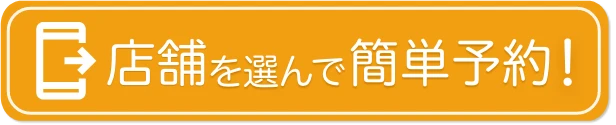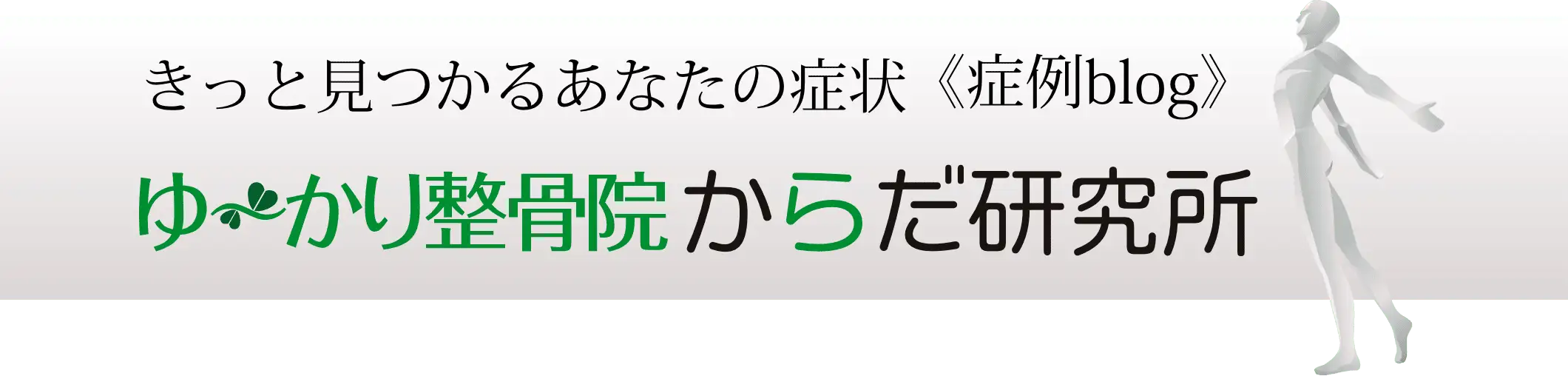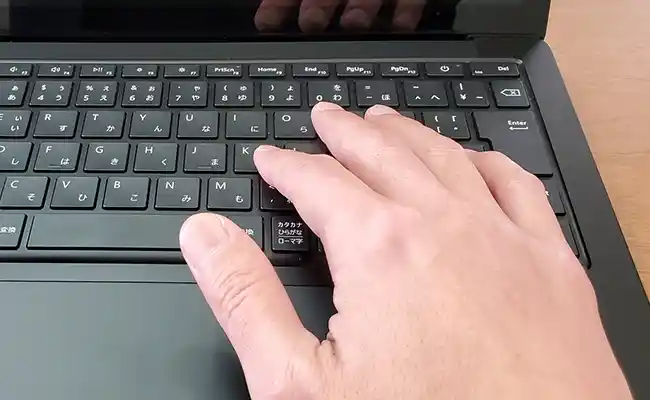打撲(内出血)

- 「打撲したんだけど、冷やしておけばOK?」
- 「早く打撲をなおして、チームに復帰したい」
- 「以前、打撲したところが、痛くなってきた」
- 「湿布を貼っているだけだけど、これで大丈夫?」
ゆ〜かり整骨院グループの打撲(内出血)の症状改善のながれ
打撲(内出血)について
打撲は、皮膚の表面には傷口がなく、皮下組織(筋繊維や血管)が損傷した状態です。
「ぶつけただけ」「そのうち治るだろう」と軽く考えがちですが、適切な処置をしないと痛みが長引いたり、慢性化してしまうリスクがあります。
早めに受診された場合、軽い打撲であれば通常1〜2週間、強い打撲でも4〜6週間ほどで改善する「急性外傷」です。しかし、受傷後に時間が経過してから治療を始めると、治るまでに3か月を要する場合もあります。
「ただの打撲だから」と放置すると、血行の悪い状態が続き、「痛みを起こす物質」が発生して血管を収縮させ、さらに血行が悪化するという「痛みの悪循環」を引き起こし「慢性の痛み」に変わってしまいます。
痛みが慢性化すると、元の皮下出血が治っているにもかかわらず痛みが続き、不安から心因性疼痛につながることもあります。そのため、早期の適切な治療が大切です。
打撲(内出血)の原因は?
〜日常生活からスポーツまで、誰にでも起こりうる打撲〜
「机の角に足をぶつけた」
「階段から転落してしまった」
「サッカーの試合中に相手と接触した」
打撲は、どのような年齢層でも発症する可能性がある発生頻度の高い外傷です。
日常生活での打撲 高齢者の場合、筋力の低下により足腰が弱くなるため、ベッドや階段から転落したり、敷居につまずいたり、何もないところでも転倒してしまうなど、姿勢バランスの崩れが原因で打撲をする場合が多く見られます。
また、老若男女問わず、椅子や机の角など固い場所に身体の一部をぶつけたり、つまずいたりなど、生活環境が原因でケガをすることも多くあります。
スポーツでの打撲
バスケットボールやサッカーなどのコンタクトスポーツでは、接触プレーによって大腿部(太もも)や下腿部(ふくらはぎ)を打撲することが多く見られます。
運動部の学生さんや社会人チームで活動している方に多く発生します。 試合中だけでなく練習中でも打撲のリスクがあるため、注意を払いながら練習を行うことが重要です。
打撲は軽視できない外傷
外見上は傷がないため軽く考えられがちですが、皮下組織が大きなダメージを受けている場合もあります。適切な処置と治療を早期に行うことで、回復を早め、慢性化を防ぐことができます
四十肩・五十肩(肩関節周囲炎)の施術の流れ
〜打撲の痛みを長引かせず、早期回復から再発予防まで〜
打撲(内出血)は「湿布を貼っておけば治る」と思われがちですが、適切な治療を行わないと回復に時間がかかり、場合によっては慢性化してしまいます。
天王町接骨院、ゆ〜かり整骨院では、打撲の回復を「初期・中期・後期・メンテナンス期」の4段階に分け、それぞれの状態に合わせた施術を行います。早期に炎症を抑え、筋肉の柔軟性を取り戻し、再発しにくい身体づくりまでサポートします。
※治療初期からメンテナンス期までの流れは、多い事例でご紹介しています。全ての方が当てはまるわけではございません。また、患部の状態によっては専門医(医師)をご紹介することもございますので、ご了承ください。
《初期》打撲(内出血)の施術
〜打撲の痛みを残さないために大事な初期治療〜
打撲の施術は、まず「痛みと腫れを抑えること」と「損傷した組織の回復を促すこと」から始まります。
この初期治療の期間はおおよそ1週間が目安です。受傷直後の対応が最も重要なため、週2〜3回程度の通院ペースをおすすめしています。治療のペースをつめて間隔を開けずに受けていただくことが、痛みを早期回復させるために重要です。
打撲した箇所は、受傷直後よりも時間が経ってから痛みが激しくなります。
これは、ぶつけた衝撃によって筋肉組織が壊れて出血を起こし、その血液が筋肉の中で鬱滞して腫れ上がるためです。そのため、打撲の初期は痛みを感じないことも多く、「大したことない」と放置してしまいがちです。
◎ハイボルテージ療法で痛みを緩和
天王町接骨院、ゆ〜かり整骨院では、治療初期にまずハイボト治療(高電位圧治療・電気鍼)で筋肉を緩めます。電気治療は神経にも作用するため、痛みの鎮静や神経の興奮を鎮める効果が期待できます。
◎柔整マッサージで血液循環を改善
次に、患部に柔整マッサージを施し、壊れた筋肉組織の中にある鬱滞している血液を散らしていくよう求心性(患部から心臓に向けて)に柔整マッサージを行い、腫れによる痛みを軽減させていきます。
この時に施す柔整マッサージは、凝り固まった筋肉(肩こりや腰痛症状)へ施すマッサージとは異なります。柔整マッサージは、国家資格を持つ筋肉と骨格のプロ「柔道整復師」が行うもので、リラクゼーション目的のマッサージではありません。
◎包帯固定で組織の硬化を防ぐ
患部を治りやすい状態に整えてから包帯固定を施し、損傷した組織が硬くなることを防ぎます。
打撲を放置していると損傷した筋肉が硬くなり、回復が遅れるばかりか、柔軟性を失った筋肉部分が後々肉離れを起こしたり、関節の可動域を狭くする原因になるからです。
施術を続けていくと、患者様から「腫れが引いてきた」「痛みが軽くなった」「動かせるようになってきた」「日常生活が楽になった」といったお声をいただくのがこの打撲の初期段階です。
《中期》打撲(内出血)の施術
〜筋肉の柔軟性と可動域を取り戻す大切な時期〜
中期では、元の筋肉組織の柔軟性を取り戻すことを目的に筋肉調整(柔整マッサージ・トリガーポイント療法)を施します。
この中期の施術期間は、初診からおおよそ2〜4週間が目安です。痛みが和らいできても、筋肉の柔軟性と可動域を完全に取り戻すためには週1〜2回の通院を継続することが重要です。ここでしっかり治療を行うかどうかで、その後の回復スピードや再発リスクが大きく変わってきます。
打撲によって損傷した筋肉からの出血(腫れ)と痛み(炎症)がおさまってきたら、本格的な筋肉の治療が始まります。筋肉組織は修復過程で収縮してしまうため、中期では元の筋肉組織の柔軟性を取り戻すことが重要です。
◎筋肉調整で可動域を広げる
治療中期では、動かせるように、関節の可動域が広がるように筋肉調整を行います。治療効果の判定としては、「順調に良くなっている=どんどん可動域が回復している」ことです。
私の経験上、大腿部を打撲して、うつぶせの膝ストレッチで45度程度(重症)しか曲げられない選手でも、治療中期、初診時から3週間目までには120度を超えてきます。
◎患者様に合わせた施術
アスリートや運動部の学生患者様には、早くフィールドに戻りたいという要望に応えるため、あえて強めの力で柔柔整マッサージ施します。(一般の患者様には、お身体の状態に合わせて優しく施します。)そして可動域の改善具合を常にモニタリングし、経過不良と判断したら、治療回数(通院頻度)を上げるよう指導させていただきます。
施術を続けていくと、患者様から「痛みがかなり減った」「関節が動かしやすくなった」「運動できるようになってきた」「日常生活が問題なくできるようになった」といったお声をいただくのがこの打撲の中期段階です。
《後期》打撲(内出血)の施術
〜日常生活への復帰と良い状態を安定させる大切な時期〜
後期では、患者様がやりたいことができるようになるために、筋肉の柔軟性と関節の可動域のさらなる改善が課題です。
この後期の施術は、通常週1〜2回程度の通院を目安に1〜2週間ほど継続するのがおすすめです。正しい身体の動かし方を身につけ、患部に負担をかけない生活習慣を定着させることで、改善した良い状態を安定させることができます。
打撲(内出血)は、発症から完治までに軽度で1〜2週間、強い打撲でも4〜6週間かかるのが一般的です。
初期・中期の施術で痛みは軽減し、筋肉の柔軟性も改善してきますが、この後期の段階では「特定の動作で違和感が残る」「スポーツや日常生活の動作で患部に不安を感じる」といった症状が出やすくなります。
◎生活スタイルに合わせた指導
ゆ〜かり整骨院では、後期の施術において患者様お一人おひとりの生活スタイルに合わせた指導を行います。施術で筋肉や関節の動きをさらにスムーズに整えるとともに、関節の動かし方・ストレッチ指導などを行い、日常生活動作の注意点や指導をしています。
◎筋持久力とスピードの回復
「動ける=筋肉の柔軟性と関節の可動域(ROM)」を取り戻したら、自分が望む日常生活動作をする中で、必要な筋持久力とスピードを回復させることが課題になります。
◎現場復帰への調整期間
治療後期は、回復間もない患部を温めて動かすため、患部が一時的に炎症状態を起こすことがしばしばあります。現場復帰への調整期間として、動いた後の痛みや不具合を日々改善させることが必要です。これを怠ると、再び痛みや腫れが出てくることがありますので、十分注意してください。
施術を続けていくと、患者様から「違和感がなくなった」「スポーツに復帰できた」「不安なく動けるようになった」「以前のように活動できる」といったお声をいただくのがこの打撲の後期段階です。
《メンテナンス期》打撲(内出血)の施術
◎打撲は再発しやすいのか
打撲を起こした部位は、一度損傷を受けているため、筋肉が硬くなりやすく、柔軟性を失っています。この状態のまま放置すると、再び肉離れや打撲を起こしやすい状態になっています。
また、姿勢バランスや筋力のアンバランスが打撲の原因になっている場合もあります。そのため、痛みが落ち着いたあとも「再発を防ぐためのメンテナンス」がとても大切です。
◎筋肉調整とストレッチ指導で柔軟性を維持
ゆ〜かり整骨院では、筋肉調整とストレッチ指導を通じて、筋肉の柔軟性を保ち、関節の可動域を維持するサポートを行います。また、再び打撲による別の部位への負担が減るように身体の使い方の指導や運動の指導も行っています。
◎EMSで体幹と下肢の筋力強化
姿勢バランスや筋力のアンバランスが打撲の原因になっている場合は、EMSを用いて体幹や下肢の筋力を強化し、転倒しにくい、ケガをしにくい身体づくりをサポートします。
通院ペースは症状や生活習慣によって異なりますが、一般的には月1〜2回の定期的なメンテナンスを続けることで、良い状態を安定させやすくなります。単に痛みを取るだけでなく、再発しにくい身体を作ることこそが、このメンテナンス期の大きな目的です。
打撲(内出血)の予防と応急処置について
〜これだけは知っておきたいファーストエイド〜
打撲は、日常生活やスポーツの中で誰にでも起こりうる外傷です。しかし、適切な予防と応急処置を知っておくことで、重症化を防ぎ、早期回復につなげることができます。
打撲を予防するために 生活環境の工夫 生活動線上にはなるべく障害物を置かないなど、転倒やぶつかるリスクを減らす環境づくりが大切です。特に高齢者の方は、段差の解消や手すりの設置なども検討しましょう。
筋力とバランス能力の維持
転倒による打撲を防ぐには、下肢の筋力と体幹のバランス能力を維持することが重要です。日常的に軽い運動やストレッチを行い、身体機能を保ちましょう。
スポーツ時の注意
コンタクトスポーツでは、適切なウォーミングアップとクールダウンを行い、筋肉を柔軟に保つことで打撲のリスクを軽減できます。また、プロテクターなどの保護具の着用も効果的です。
打撲が起きた時の応急処置(PRICES処置)
スポーツにはケガがつきものです。十分な予防を行なうことは大前提ですが、ケガをすること自体はスポーツではある程度やむを得ないと考えます。そこで重要なのは、ケガをした時の対処方法です。ケガに正しく対処できるか否かは、その後のスポーツ人生を左右しかねない重要なポイントになります。
ケガ(打撲、捻挫、肉離れ)が起きたらすぐにPRICES処置を実施する必要があります。 PRICESとは、応急処置に必要な事項を英語表記し、その頭文字を取ったものです。これは別名、ファーストエイドと呼ばれます。
- P:Protection(保護)
ケガした部位を保護し、それ以上不必要なダメージを与えないようにする。フィールドでは、まず選手を安全な場所に移動させることから。 - R:Rest(安静) 各5秒×3セット)
患部を動かさない。安静にしておくことで、腫れや炎症を抑え、出血を最小限に食い止める。 - I:Ice(冷却)
患部を冷やすことで、毛細血管を収縮させて血液の流れを抑制し、痛みを和らげる。 - C:Compression(圧迫)
患部を弾力包帯、ラップなどで圧迫することで、内出血を抑え、組織に血腫(血のかたまり)ができることを防ぐ。 - E:Elevation(高挙)
患部を心臓より高い位置に持ち上げ、内出血を軽減させる。 - S:Support(補助)
三角巾で腕を吊る、松葉杖をつくなど、患部に負担をかけない。
効果的なアイシング方法 この中で、早期回復で重要なのは「I:Ice(冷却)」です。 その「I:Ice(冷却)」における大きなポイントは次の2つです
1.ビニール袋を2重にする
氷のう袋があれば良いですが、一般的なレジ袋や透明のビニール袋に氷を入れて使用しましょう。その時、凍傷を防ぐためにビニール袋を二枚に重ねます。何度もアイシング経験がある方はビニール袋1枚でもOKです。 ケガのアイシングの時間は「20分冷やしたら5分休憩」を寝るまで行えれば理想的です。
2.氷と一緒にほんの少しだけ水を入れる
氷が熱を奪う瞬間は「溶ける時」なので、氷が溶けるのを待つのではなく、早く熱を奪うように最初からほんの少しだけ水を入れると良いです。
補足:急激に冷やしたい時には、氷と塩で! 氷に塩を混ぜると融ける速さが増して急激に熱を奪います。さらに、氷が融けてできた水に塩が溶けていき、この時にもまわりから熱を奪います。この2つが一緒になって、まわりの温度が0℃以下にまで下がります。
当院での予防指導 天王町接骨院、ゆ〜かり整骨院では、施術とあわせて身体の使い方やストレッチ方法を指導しています。ご自宅で継続することで、再発予防にもつながります。
打撲(内出血)についてよくある質問(FAQ)
Q.打撲は放っておいても自然に治りますか?
A. 軽度の打撲であれば自然に治ることもありますが、適切な処置をしないと治るまでに時間がかかり、慢性化するリスクがあります。早期に施術を受けることで、回復スピードが早まり、後遺症を防ぐことができます。
Q.打撲と肉離れの違いは何ですか?
A. 打撲は外からの衝撃で筋肉や血管が損傷した状態で、肉離れは筋肉が急激に収縮して筋繊維が断裂した状態です。どちらも痛みと腫れを伴いますが、原因と損傷のメカニズムが異なります。
Q.改善までにはどれくらいかかりますか?
A. 個人差はありますが、軽い打撲で1〜2週間、強い打撲でも4〜6週間ほどで改善します。ただし、受傷後すぐに適切な処置を行うことが重要で、放置すると3か月以上かかる場合もあります。
Q.通院の頻度はどのくらいですか?
A. 急性期は週2〜3回の集中的な施術で炎症を抑えます。中期は週1〜2回で筋肉の柔軟性と可動域を広げ、後期以降は週1〜2回程度で良い状態を安定させます。症状が落ち着いたら、月1〜2回のメンテナンスがおすすめです。
Q.湿布だけでは治らないのですか?
A. 湿布は痛みを和らげる効果はありますが、鬱滞した血液を流し、筋肉の柔軟性を取り戻すには専門的な治療が必要です。湿布だけでは回復に時間がかかり、筋肉が硬くなってしまうリスクがあります。
Q.自宅でできる予防法はありますか?
A. はい。生活動線上の障害物を減らす・筋力とバランス能力を維持する運動・日常的なストレッチが有効です。当院では再発を防ぐための身体の使い方も指導しています。
Q.スポーツにいつ復帰できますか?
A. 痛みが落ち着き、筋肉の柔軟性と関節の可動域が十分に回復してからの復帰が望ましいです。無理に早期復帰すると再発や肉離れのリスクが高まります。担当の柔道整復師と相談しながら、段階的に復帰しましょう
Q.以前打撲した箇所が痛むのはなぜですか?
A. 打撲後に筋肉が硬くなったまま放置されている可能性があります。損傷した筋肉は柔軟性を失いやすく、再び痛みが出やすい状態になっています。メンテナンス治療で筋肉の柔軟性を取り戻すことが大切です。
監修:ゆ〜かり整骨院グループ 株式会社アザース 柔道整復師チーム
※柔道整復師とは、骨折、脱臼、打撲、捻挫などの外傷に対し、手術や薬に頼らず、手技療法や物理療法、運動指導を駆使して、患者の自然治癒力を最大限に引き出す治療を行う国家資格を持つ医療技術職です。
打撲については下記に各院にご相談ください。
《症状改善の流れ》あなたのお悩みはどれですか?
肩こりを治すとゴルフのスライスが直る!
2026年2月2日
筋骨格系の専門家が語る「肩こり」と「ゴルフ上達」の深い関係 かつてゴルフといえば中高年のレジャーというイメージが強いものでした。 しかし現在では状況が大きく変わっています。松山英樹選手のマスターズ制覇や渋野日向子選手の全 […]
ゴルフスライス巻き肩肩こりふくらはぎが痛くて歩けない……「肉離れ」
2025年9月20日
ふくらはぎの「肉離れ」その原因とは? ふくらはぎの肉離れは、スポーツの場面でよく起こる代表的な外傷です。 たとえば、膝を曲げた状態でジャンプするときや、地面を強く蹴った瞬間などです。テニスでボールを追いかけるときの後ろ足 […]
サッカースポーツ外傷ふくらはぎの痛み肉離れ朝起きたら、首が大変なことに!「寝違え」
2025年9月20日
寝違えて首が痛くなってしまったら…… 寝違えの多くは、寝ているときの姿勢が原因です。長時間にわたり首に負担がかかる体勢が続くことで、痛みが出やすくなります。 痛みがあるときは炎症が起きています。自己流でストレッチやマッサ […]
ストレッチ寝違え首の痛み